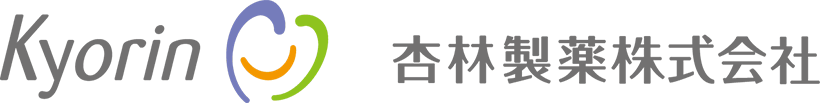杏林製薬という会社仕事について
わたらせ創薬センター
探索研究新しい薬の種を生み出す
創薬研究とは病気を引き起こすメカニズムを調べ、その原因となる因子に照準を絞り、その治療に有効と思われる新薬の種(シーズ)をつくり出すこと。“0から1を生み出す”仕事です。シーズが最終的に新薬となり医療現場へ送り出される確率は3万分の1ともいわれ、ひとつの新薬開発には平均15年以上が費やされます。杏林製薬では、重点領域を中心に、革新的な新薬を生み出す体制を構築。創薬の中でもファースト・イン・クラスと呼ばれる、新規性・有用性が高く、従来の治療体系を大幅に変えるような独創的な医薬品を生み出す取り組みに重点を置いています。

開発研究薬の種を医薬品へ育て上げる
創薬研究で生み出されたシーズ(種)を医薬品に育て上げます。グローバルな視点で積み上げたデータをもとに申請を行い、それが承認されてはじめて新薬が誕生します。キーワードは「スピード・科学性・信頼性」。何度試しても同じ結果が出る確かさが求められる一方で、開発コストの軽減やスピードアップも図っていかなければなりません。杏林製薬では、リード最適化から初期臨床試験までを、組織の枠を超えたひとつのチームで一貫して進めていく制度の導入や、また研究プロセスの一部をアウトソーシングするなどにより、スピードアップを図っています。

臨床開発センター
臨床開発医薬品を世に出す
臨床開発の役割は、新しい医薬品や医療機器候補の人での安全性や有効性を評価し、いち早く承認申請へつなげることです。安全性や有効性を評価するために治験計画を策定し、規制当局と相談しながら計画に基づいた臨床試験を医療機関と連携して実施します。臨床試験で得られたデータを統計学的な手法を用いて分析し、各国規制当局(日本ではPMDA;医薬品医療機器総合機構)へ申請します。臨床開発の仕事は、探索研究、開発研究から受け取ったバトンを承認まで運びきることです。

メディカルアフェアーズ医薬品の価値を最大化する
メディカルアフェアーズ(MA)は、医療関係者、アカデミア、外部研究機関等に対し、強固なパートナーとなる役割を担いながら、疾患の発生頻度や原因を探求する観察研究や、医薬品の安全性と有効性を評価する臨床研究を実施・サポートし、新たなエビデンスを構築します。様々な研究を通じた疾患周辺情報の重層化によって製品価値向上につながるのが理想です。MAは、患者さんに最適な医療が届き、さらなる医学の進歩や医療の発展に貢献することを目指して活動しています。

MRの役割情報を提供し、収集し、伝達する。医療現場でもチームをつくる。
MRとはMedical Representativeの略です。病院や薬局などを訪問し、医薬品を正しく使用してもらうために使用法や効果、副作用や安全性などの医薬情報を伝え、処方を通して患者さんの治療に貢献する仕事です。医師・薬剤師はこれらの情報を参考にするため、MRは大きな影響力があると言えます。また、医療の場での薬の効果や副作用の情報を収集し、自社にフィードバックすることもMRの重要な仕事の一つです。医療関係者とのより質の高いコミュニケーションを図るために、医療機関を訪問し直接医師と面談するリアル面談を軸として、デジタルチャネルを融合し、インパクトの残るディテールを行う活動を推進しています。

チーム制一人ひとりが主体的に動くことで、チームとして成長できる。
医療関係者のニーズを的確に把握し、より速やかに対応できる組織にするため、杏林製薬では一定のエリアを複数のMRで担当する「チーム制」を導入しています。チームだからといって個々人の役割が曖昧になることはありません。MRとしての主体性や自主性が尊重され、メンバー同士はお互いに切磋琢磨しながら、競争し高め合う存在となります。チームとしての目標が定められ、それを達成するために一致団結し、環境変化に対しては柔軟性をもって活動しています。年に1回、目標を達成したチームの中で、より成果をあげたチームに対して、「アプリコット賞」を授与。一人ひとりが主体となりながら、チームで目標を達成する喜びをMR同士が感じ合える企業風土づくりを促進しています。

地域完結型医療エリアを網羅するチーム制を生かし、医療機関・医療従事者のニーズに対応する。
超高齢化社会では、複数の疾病を抱える老齢期の患者さんが中心となります。そうした時代の医療は、病気と共存しながらQOL(Quality of Life)の維持・向上を目指す医療となります。すなわち病院で疾病を完治させる「病院完結型」から、患者さんが生活していくために地域で支える「地域完結型」の医療へとシフトしています。その実現のためには、様々な医療機関の連携、総合的な支援のネットワークが必要となります。エリアチーム制を取っている杏林製薬は、大学病院、基幹病院、開業医をひとつのチームで網羅する体制であり、「地域完結型医療」のネットワークをつなぐ重要な役割を果たせる環境にあります。