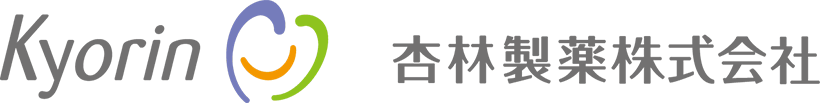職種別座談会開発職
Profileプロフィール

R.K.
臨床開発センター
開発部
2023年 新卒入社
薬学部 薬学科

S.K.
臨床開発センター
開発部
2023年 新卒入社
薬学系研究科

M.K.
臨床開発センター
開発部
プロジェクトリーダー
(治験責任者)
2002年 キャリア入社
薬学部 薬学科

M.H.
臨床開発センター
開発部
モニタリング責任者
2011年 新卒入社
薬学研究科
医療薬学専攻
小児を対象とした新薬開発は初めての経験。
そのため、プロジェクトは企画ステップから
難航した。

M.K.
今日集まった4人が携わっているのは、小児に関わる臨床開発プロジェクトです。成人向けとして上市されていますが、小児向けにはまだ承認されていない薬剤の小児への適応拡大を目指しているのが今回のプロジェクトですね。

M.H.
治験責任者であるM.K.さんがプロジェクトのリーダーを担い、私がモニタリング責任者というポジションで現場を統括。S.K.さん、R.K.さんの若手2人はCRA(臨床開発モニター)業務を担当しています。プロトコル(試験実施計画書)の検討など開発の企画がスタートしたのは2021年頃だと思います。

M.K.
この疾患で新薬はまだ小児向けには承認されていないため、患者さんや家族からの期待はとても大きいと感じます。一方、小児を対象とした臨床開発は、独自性が高く制約が多いため、プロジェクトは企画段階から難航しました。
少し専門的な話をすると、今回の臨床試験では、検査のために頻繁に採血をしなければなりません。けれども、被験者が小児のため、その回数を慎重に検討する必要があるあります。数少ない採血で科学的に妥当な結果を得るため薬理薬物動態研究所のメンバーやこの領域を専門とする医師を交え、何度も議論を重ねました。

M.H.
今回の試験は安全性の確認が一つの重要なポイントだったので 妥協はできないですよね。ちょうど私にも幼い子どもがいて、「被験者が自分の子どもだったら」ということを常に思い浮かべながら計画を立案しました。

M.K.
そうして臨床試験が立ち上がったのが2022年ですね。

M.H.
若手のお二人がプロジェクトに加わったのはその翌年かな?

S.K.
はい。私たち2人が杏林製薬に入社したのが2023年。入社1年目から大きなプロジェクトにアサインされてびっくりしました(笑)。

M.K.
最近の製薬会社では、治験の実務的な進行は外部のCRO(開発業務受託機関)に委託し、最少人数のメンバーで開発を進めるスタイルが主流になりつつあります。けれども、今回はぜひ若手に経験を積ませたいという会社の意向で、内部での実施を決断しました。

なかなか最初の一歩が踏み出せず、
あえて自分にプレッシャーをかけてみた。

M.K.
このプロジェクトでは乗り越えなければならない壁がいくつもありました。なかでも難航したのが、臨床試験に参加していただく被験者をいかに集めるか、症例の積み上げですね。

M.H.
ええ。各メンバーがCRAとして複数の医療機関を担当し、症例集めに奔走しました。ところが、なかなか試験で設定した目標数に達しない。若手の2人には入社早々責任のあるミッションを任せることになりました。

R.K.
最初はOJTとして先輩のお二人に同行して学び、CRAとして医療機関を任されるようになったのは半年後くらいでしょうか。症例が思うように集まらなかったことから、担当の医師に許される範囲での、近隣の開業医との連携を依頼したり、病院内に告知ポスターを掲示したりといろいろ活動を進めました。実際の活動はCRCを通じて展開することが多いため、最初はそのあたりの連携も難しかったですね。

S.K.
私はその最初の一歩がなかなか踏み出せず、あえて自分にプレッシャーをかけました。とりあえず医師とのミーティングの日時を決めてしまったのです。その日を目指して必死に資料を準備し、M.K.さんにもフォローしてもらってどうにかミーティングを成功させました。ここから前向きに歯車が回り出しました。とても印象に残っています。

M.H.
S.K.さんは意外に豪胆なところがあるね(笑)。一方、R.K.さんは周到に準備をして緻密に進めるタイプですね。私は臨床開発に携わって十数年のキャリアがあるけど、若手の2人からは学ぶことがたくさんあります。

S.K.
いやいや、大先輩の2人には同行して現場でノウハウを教えていただくなど、とてもお世話になっています(笑)。

M.K.
若手の2人にはCRAとしての自分のスタイルを見つけてほしいと思い、基本的な活動は任せています。リーダーとして気を配っているのは、メンバーたちが悩みや課題を一人で抱え込まないようにするためのチームとしての雰囲気づくりですね。

M.H.
杏林製薬の開発チームには、苦労も喜びも一緒に分かち合おうという姿勢が感じられますね。難航していた症例集めも目標に達して、いまはホッとした空気がチームに漂っている時期です(笑)。

モニタリング業務を主軸に
計画立案や申請資料作成にも携わり、
臨床開発
としてのキャリアの幅がぐっと広がった。

M.K.
M.H.さんが言ったように、プロジェクトは臨床試験が完了し、現在は今後のプロジェクト全体の進め方を検討するステップ。製薬会社によってはこのような臨床開発のプロセスを分担することがありますが、杏林製薬なら、モニタリング業務を主軸にして開発に関するすべての業務に携われるチャンスがある。それが一番の魅力だと私は感じています。

M.H.
臨床の最前線で、医師をはじめたくさんの人たちと一緒に新薬を開発していくのは、CRAならではの醍醐味ですね。でも、モニタリング業務の研鑽を積むと、それ以外にもチャレンジしてみたいという気持ちになると思うのです。私は自分から手をあげて、入社3年目くらいにプロトコルの作成、入社7年目くらいに申請資料の作成などにも携わるようになり、臨床開発としてのキャリアの幅がぐっと広がりました。

R.K.
私も現在はプロジェクトの方向性を左右する資料の作成に携わっているのですが、そこで得た知識がCRAとしての活動にもフィードバックされていると思います。医師との面談で、新薬の未来について意見を交わせるようになるなど、成長している自分を実感しますね。

S.K.
風通しのよい組織も、この会社ならではの特徴ですよね。他部署の先輩にも気軽に相談できる雰囲気があります。

M.H.
実際、開発部がいるオフィスはフリーアドレス制になっていて、いろいろな部署のメンバーと隣り合わせで仕事ができる環境ですしね。
杏林製薬の臨床開発は、計画立案から実施、当局との交渉まで、多様な部署と連携しながら進めていく仕事です。私たち開発部のミッションは、杏林製薬の研究開発のハブになることだと私は思っています。

「ぜったいにやり遂げよう」と背中を押され、
臨床開発のやりがいの大きさ、責任の重さを
再認識した。

M.K.
若手の2人は、このプロジェクトを通じてどのような経験を積んでいると感じていますか?

S.K.
そうですね。先ほどM.H.さんが「臨床開発の第一線に立つ」という話をしましたが、まさにその感覚を体感しています。私は大学院で薬科学を専攻し、基礎的な研究ではなく、臨床に近い場所で創薬に貢献したいと考えて開発職を志望しました。臨床開発のやりがいや意義を現場で感じて、新薬を患者さんに届けていきたいという想いがさらに強まりましたね。

R.K.
私も同じ気持ちですね。臨床開発に携わっていると、疾患で苦しんでいる患者さんの声がたくさん集まってきます。それと同時に、開発に関わるたくさんの人が「この新薬をぜひ承認につなげましょう」といった想いを持っています。臨床開発のやりがい、そして責任の重さを知り、今後は少しでも早く新薬を届けるために、開発戦略の立案などにも携わってみたいと思うようになってきました。

M.H.
私も、いま2人が感じているようなマインドをこれからもずっと大切にしていこうと思っています。「あの薬、よかったよ」と医師や医療従事者、CRCから言ってもらえるような臨床開発に取り組んでいきたいですね。

M.K.
このプロジェクトは、小児向けとしては初の新薬ということもあって、初めて経験するようなことばかりです。正直言ってリーダーの私自身、心が折れそうになったこともあります。そんなとき、医師から「絶対にやり遂げないとだめだよ」と声をかけられ勇気づけられました。みんなの想いを遂げるためにも、この新薬を1日でも早く患者さんに届けたい。さらに将来は、このメンバーたちと一緒に、希少疾患の新薬にもチャレンジしてみたいですね。