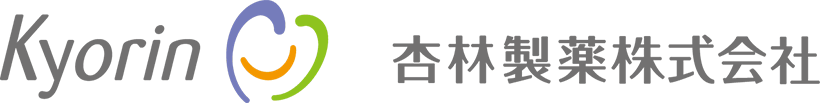職種別座談会研究職
Profileプロフィール

M.F.
わたらせ創薬センター
薬理研究所
2014年 新卒入社
薬学研究科

D.T.
わたらせ創薬センター
薬理研究所
2019年 新卒入社
理工学研究科

M.Y.
わたらせ創薬センター
薬物動態研究所
2008年 新卒入社
農学研究科

T.M.
わたらせ創薬センター
安全性研究所
2006年 新卒入社
新領域創成科学研究科
多様な研究所から精鋭たちが集まり、
困難な探索研究のプロジェクトが動き始めた。

M.F.
今日集まった4人は、わたらせ創薬センターで進められている新薬研究プロジェクトのメンバーです。最初に自己紹介も兼ねて、これまでの簡単なキャリアを聞きましょうか。一番キャリアが長いのは、安全性研究所のT.M.さんかな。

T.M.
そうですね。私が入社したのは2006年です。これまで主に探索ステージの安全性評価に携わってきました。比較的アーリーな時期では、安全性と薬理の研究は表裏一体のようなところがあり、薬理研究グループにも所属していたことがあります。

M.Y.
次にキャリアが長いのが私ですね。入社以来ずっと薬物動態の研究に携わっています。私のキャリアにとって転機となったのは入社3年目です。それまで非臨床・臨床ステージに関わっていたのですが、配属が変わり探索ステージの薬物動態を担当することになったのです。この研究が自分に合っていたというか、やりがいを見つけて、以来どっぷりと探索薬物動態の研究に取り組んでいます。

T.M.
M.Y.さんの場合は、まわりから見ていても探索の方がぜったいに合っているような感じがありますよね。とてもパワフルな研究者です(笑)。

M.Y.
そうですか(笑)。残りの2人はどちらも薬理の研究者ですね。M.F.は、今回の開発プロジェクトのリーダーでもあります。

M.F.
ええ。私は入社11年目です。ずっと薬理の研究に携わっています。印象に残っている経験をあげるとするならば、7年目から携わった新薬研究プロジェクトですね。初めてリーダーを任されたのですが、臨床ステージへとステップアップできませんでした。あの時の悔しさもあるので、今回のプロジェクトには思い入れがあります。

D.T.
私は入社6年目です。1年目からアーリーなものも含めて大きなテーマを複数任されて驚きました。このプロジェクトに携わるようになったのは3年目からですね。

T.M.
D.T.さんは若いけど、とても真面目で優秀な研究者です。難しそうな実験もさらっとこなしてしまうなど、クールな印象があります(笑)。逆にD.T.さんから見ると、M.F.さんはどんな研究者ですか?

D.T.
研究者としてすごい人であり、頼りになる先輩です。いつでも親身に相談に乗ってくれますし、M.F.さん自身がわからないことでも「あの先輩に聞くといいよ」などと的確にアドバイスしてくれます。

M.Y.
ほんとうですか(笑)。

免疫・炎症性疾患をターゲットとした新薬研究。
生体レベルでの評価研究で
大きな壁にぶつかった。

M.F.
今回の新薬研究プロジェクトは、免疫・炎症性疾患をターゲットにしたものです。わたらせ創薬センターでプロジェクトが動き出したのは、7年前くらいでしょうか。

T.M.
このプロジェクトは少し特殊で、杏林製薬が共同開発を当時米国の子会社とともに進めており、薬理のM.F.さん、薬物動態のM.Y.さんが中心になって、米国とやりとりしながら化合物を探索してきました。

M.Y.
そしてin vitroで非常に薬効のある化合物を見出したのですが、そこで大きな壁にぶつかったわけです。

M.F.
そもそもこのプロジェクトのターゲット因子はヒト特有であり、通常、私たちが実験で使用する齧歯類の動物では機能を示さないものです。つまり、in vivoでの評価が非常に難しい。そこで、適正な評価が行える動物モデルを実現するための薬理の研究が始まりました。

D.T.
私がプロジェクトにジョインしたのは、ちょうどこの動物モデルの研究が始まった頃だったと思います。

M.F.
具体的に言うならば、遺伝子改変マウスの作製です。遺伝子の改変に加えて、その改変したターゲット因子がマウス体内で機能を示し、疾患に関わるようになっているのかなどを評価していかなければならない。そこで大きな仕事をしてくれたのが、D.Tさんですね。

T.M.
試行錯誤の末に動物モデルが確立されてin vivoでの評価が可能になった。私たち安全性の研究者が本格的に開発に関わってくるのは、このあたりのステップからです。

M.F.
評価研究が進むにつれ、in vivoでもin vitroと矛盾しないような薬効が発揮されることがわかってきた。「おお、これはすごいぞ!」とプロジェクトチームの士気も高まりましたね。

M.Y.
プロジェクトが加速するとともにメンバーも増えてきました。薬理研究所からは数名、薬物動態と安全性の研究所ではほぼすべてのメンバーがなんらかの形で関わりました。薬理研究とともに、この大所帯のプロジェクトチームをまとめていったのがリーダーのM.F.さんです。

同じ目標に向かって「個」が持てる力を
最大限に発揮する。
その結果として、自然な形でチームが成り立っている。

T.M.
M.F.さんはプロジェクトチームをまとめていくために特別気にかけているようなことはありますか?

M.F.
そうですね。仮説・検証というサイクルをいかに的確に回していくかということを意識しています。何か問題がありそうなら、それぞれの研究チームの代表であるT.M.さんやM.Y.さんにすぐ相談していますし。チームとしての連携はとてもスムーズだと思いますね。

M.Y.
メンバーみんなで目標を共有して、各自が的確に判断しながら最短ルートで進んでいくような雰囲気がありますね。その結果として、自然な形でチームが成り立っているような感じです。もっともこれは特別なことではなく、私たちが普段からわたらせ創薬センターで慣れ親しんでいるスタイルです。

T.M.
それは私も感じます。そもそもこのセンターの環境がとてもオープンで快適です。研究員たちがいるスペースは2フロアあるのですが、吹き抜けの階段でつながっていて自由に行き来ができます。フロアも仕切りなどがなく、デスクから立ち上がって眺めるだけで他の研究チームの様子がわかります。「おっ、ちょっと話に行ってみようか」と気軽に相談する気になれるのです。

M.Y.
T.Mさんは研究者として優秀なばかりでなく、人柄もよくてみんなからとても頼りにされていますね(笑)。若手のD.T.さんは杏林製薬の環境についてどう感じていますか?

D.T.
私は学生時代、薬学専攻ではなくて、最初は創薬の研究員としてやっていけるか不安がありました。けれども、配属早々から薬理ばかりでなく他の研究所の先輩たちまでが親身に教えてくれて、とても心強かったですね。もう一つ、わたらせ創薬センターの魅力をあげるとすると、若手のうちから責任あるテーマを任せられることでしょうか。

M.F.
このプロジェクトでのD.T.さんの活躍がまさにそうですしね。チームに加わってすぐに力を発揮できたのは、それまでに充実した経験を積んできたからこそだと思っています。

新薬開発のバトンは、
いよいよ臨床開発ステージへ。
患者さんに届くところまで見守り続けたい。

M.F.
プロジェクトはもうすぐ臨床開発ステージにステップアップする段階にあります。現在、そのための最終となる実験を進めているところです。

T.M.
研究部門としては、臨床開発に受け渡すまでがひとまずゴールですから、旅立っていく新薬を見送るような気持ちですね。

M.Y.
ところが、私は薬物動態の責任者として、この新薬を臨床ステージでも継続して受け持つことになったのです。探索から臨床まで携わるのは貴重な経験ですので、ぜひ新薬が患者さんに届くところまで見届けたいですね。

M.F.
薬理としてもこのステップで手が離れるのですが、臨床ステージになっても新薬の付加価値を高めるための研究が必要となります。ここまで育ててきたのですから、ずっと見守っていきます。

D.T.
私は、若手のうちからほんとうに幸せな経験を積ませてもらっていると感じています。自分にはまだ子どもはいないのですが、まるで新薬の親になったような気持ちです(笑)。将来は、もしチャンスがあるなら、自分で探索した新薬を上市するような開発に、プロジェクトリーダーとして携わってみたいです。

T.M.
今日の4人の話からも伝わると思うのですが、このプロジェクトでは誰もがほんとうに気持ちよく前向きに仕事をしています。これからは、そんな楽しさを若手の研究者たちに伝えていけるような環境づくりにも取り組んでいきたいですね。