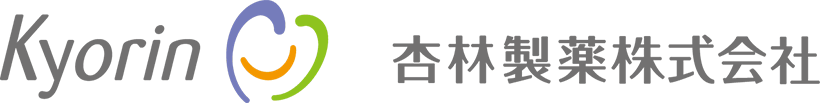特別編集みんな、新人だったんだ。
Profileプロフィール

S.T.
[研究員]
わたらせ創薬センター
安全性研究所
2020年入社 新卒入社
生命環境科学域 獣医学類

A.K.
[研究員]
わたらせ創薬センター
合成研究所
2021年入社 新卒入社
薬学研究科 薬学専攻

M.S.
[MR]
東京支店
多摩第二営業所
2020年入社 新卒社員
人間環境学部 人間環境学科

Y.K.
[MR]
首都圏支店
厚木第一営業所
2018年入社 新卒社員
薬学部 薬学科
ふだん接する機会がない研究員とMR。
話がどんな展開になるのか、少し緊張している。

Y.K.
私とM.S.さんが支店のMRで、S.T.さんとA.K.さんがわたらせ創薬センターの研究者。同じ会社でもMRと研究者は話す機会もほとんどなく、お互いの仕事もよく知りませんよね。

S.T.
確かに。今日は楽しみであると同時に、少し緊張しています(笑)。

Y.K.
最初に自己紹介を兼ねて仕事の話を少ししたいと思います。私は2018年の入社で、MRとして7年目です。北海道支店に6年いて、昨年、首都圏支店の厚木第一営業所に異動してきました。

M.S.
私もY.K.さんと同じMRで、入社5年目です。東京支店の多摩第二営業所に所属しています。4人のチームで活動していて、私は主に開業医を担当しています。
私とS.T.さんは同期入社なので、研修で顔を合わせたことがありますよね。

S.T.
そう。2020年の入社で、私も5年目。わたらせ創薬センターの安全性研究所に所属しています。創薬研究の中でも、安全性研究の役割は一般的にイメージが湧きにくいかもしれません。薬の“種”となる候補化合物に対して、医薬品の開発上、問題となる毒性があるのかないのかを判断し、毒性がある場合には開発中止の判断をするか、どうやったら回避できるかなどを検討しています。その中でも私は、毒性のメカニズムを解き明かす研究を担当しています。

A.K.
私が所属する合成研究所は、創薬の上流を担う研究部門です。入社3年目までは、探索合成研究という、世の中にまだない化合物をつくってそれがターゲットに効くかどうか調べる研究に携わっていました。現在は開発合成グループに異動し、実験室レベルでの合成を製造レベルにスケールアップするための研究に取り組んでいます。
ところで、私たちの研究についてできるだけかみ砕いて話しているつもりなのですけど、イメージはつかめそうですか?

M.S.
うーん……、難しい(笑)。

完璧な人間はいないのだから……。
その先輩のひと言で肩から力が抜けた。

S.T.
私は学生時代、獣医学専攻でして毒性関連の研究に携わったことがなかったため、配属されてしばらくは右も左もわからないことばかりでした。それでも新人の頃から一連の研究を主体的に任され、先輩たちにたくさんアドバイスされながら経験を積み、成長できたと感じています。

M.S.
その気持ち、わかります。私は文系出身だったため、製薬は未知の世界でした。それに性格的に完璧主義みたいなところがあって、最初の頃は一人で悶々と悩んでいました。そんなある日、先輩が声をかけてくれました。「一人で乗り越えようとせず、まわりを頼っていいんだよ、完璧な人間はいないのだから」と。この言葉で肩から力が抜けたことを憶えています。皆さん、そんな経験はありますか?

Y.K.
私は営業所長から「新人はミスをするのが当たり前。たくさん失敗して次に活かせ!」とよく声をかけられました。というのも、私は慎重なところがあって、石橋を3回たたいてから渡るような仕事の進め方だったのです(笑)。

A.K.
私は、学生時代から化学合成を専門としてきましたし、そもそもポジティブな性格なので、壁にぶつかったような記憶はあまりありませんね。上司も、私に輪をかけたようなポジティブな人で、「まずは創薬合成を楽しもう!」とアドバイスしてくれました。そもそも私たちが取り組む化学合成から新薬が生まれる確率は約3万分の1ともいわれていて、ある程度自由奔放で前向きなマインドがないと務まらない研究でもあるのです。上司からはよく「若手らしい新しい風を吹き込んでくれ」と言われています。

S.T.
合成の研究者は、わたらせ創薬センターの中でも独特の雰囲気を醸し出している人が多いですよね。食堂などで一緒になっても、だいたいすぐにわかりますから(笑)。

穏やかな人が多く、オープンな雰囲気。
研究所の食堂で、社長と一緒に
ランチしたことも。

Y.K.
入社して最初に配属された北海道支店では、穏やかで優しい先輩ばかりでとてもアットホームな雰囲気でした。北海道の人ならではの特徴なのかなと思っていたら、異動してきた現在の首都圏支店でも同じでした。どうやら杏林製薬全体に共通する風土のように感じています。

S.T.
それは研究や開発の部門でも同じではないでしょうか。私の場合、就活の時に会った人事担当の人たちの雰囲気がとてもよくて、それが入社の決め手になりました。けれども、研究部門は違うのではとちょっと心配していたのです。でも、まったくギャップがありませんでしたね。

M.S.
私も、S.T.さんと同じです。あまりにギャップがなくて逆に驚いたくらいです。

Y.K.
他社のMRの話を聞くと、「自分が……」とまわりを蹴落としてでも実績を追求する人もいるみたいですが、この会社にはそんな雰囲気はありません。

A.K.
研究部門でも同じですよね。

S.T.
時には熱くぶつかり合うこともありますが、あくまでも研究上の議論でのことであり、終われば、和気あいあいと一緒にランチしたりしています。

A.K.
役職や部署といった垣根がなく、オープンな雰囲気も特徴だと思います。わたらせ創薬センターでは、食堂でランチをする研究員が多いのですが、社長が来所される事があります。私は、社長と一緒にランチしながら研究の話をしたことがあります。

Y.K.
それはすごい(笑)。さすがに私たちは経験がないですね。

A.K.
この話を家族にしたら、「杏林製薬はすごい会社だな」と驚いていました(笑)。

M.S.
部署の垣根が低いということは営業部門でも同じだと思います。杏林製薬の大きな特徴に「チーム制」がありますが、現場のチームばかりでなく、部署や部門の枠組みを超えた心地よいチームワークを感じることがよくありますね。

こうして楽しく語り合えることが、
なによりもの杏林らしさだと思う。

A.K.
新人の頃はガムシャラに化合物をつくっていたような気がします。それが3年目くらいからでしょうか、自分なりに戦略を立てて研究を進めるようになってきました。そして4年目に違うグループに異動したわけですが、それまでの創薬の知識がバックボーンになって比較的すんなり新しい研究に入れて、成長した自分を実感しています。

S.T.
私も、少しずつ自信が持てるようになったのは、3年目くらいからだと思いますね。最近では、先輩たちのテーマにも自分なりに理論立てて意見を言う機会が増えてきて、杏林製薬の創薬に貢献しているという実感が増してきました。

Y.K.
私は、北海道の頃は、担当は開業医が中心。それが新しく異動して、基幹病院の比重が増しました。そこでまた壁にぶつかっているのですけど、自分なりに情報を集めて戦略を考えて粘り強くアプローチできるようになったと思います。

M.S.
私は、チームでの活動に加えて、営業所全体における品目の推進を任されています。最近、チームの枠組みを超えてメンバーたちを巻きこんでいく活動を進め、それが営業所の実績にも表れつつあります。

S.T.
MRの2人は、今後どのような仕事をしていきたいのですか?

Y.K.
そうですね。私は、MRとしての大きな目標となる大学病院担当を目指したいと思っています。チームリーダー、さらには統轄職といったマネジメントの仕事にも興味があります。

M.S.
私も今後は基幹病院の担当も増やし、MRとしての経験値を高めていきたい。また、女性MRが快適に働ける環境づくりにも貢献できたら嬉しいですね。S.T.さんたちの目標は?

S.T.
私は、自分自身のバックグラウンドを活かしつつ、プログラミング言語を使った解析技術なども学び、データ駆動型の毒性研究にチャレンジしていこうと思っています。

A.K.
私の目標はただ一つ。合成研究者としてホームランを打ちたい。自分が見出した化合物から新薬を創り出すことです。

Y.K.
たとえ部門が違っても、大切にしている優しさとか、心の底にある熱さとか、杏林製薬としてみんな同じ想いを持っていることを知れて、今日はとても貴重な機会だったと思いますね。

M.S.
私も、普段扱っている新薬を創り出していく同世代の仲間の話を聞けて、さらに自信を持って医師たちに広めていこうという気持ちになりました。

S.T.
部門の垣根をこえて楽しく語り合えることも、杏林製薬らしさなのかもしれないですね。

A.K.
私もそう感じています。皆さんのいい笑顔がすごく印象的でした。みんなたいへんなこともあると思いますけど、明日からも笑顔で仕事に向き合っていきたいですね。