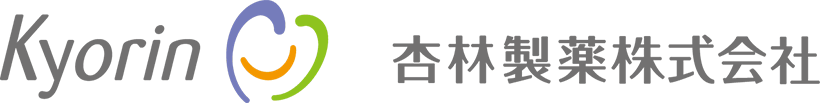特別編集チームって、なんですか。
Profileプロフィール

S.O.
[研究]
わたらせ創薬センター 薬理研究所
2020年 新卒入社
薬学府

M.S.
[開発]
臨床開発センター
開発部
2014年 新卒入社
新領域創成科学研究科

M.T.
[MR]
首都圏支店
千葉第三営業所
2016年 新卒入社
獣医学部
生物環境科学科

T.N.
[MR]
東京支店 城東営業所
2017年 新卒入社
薬学部 薬学科
創薬の源流から、医療の最前線まで。
杏林製薬には、色とりどりのチームがある。

M.S.
今日は研究、開発、営業という各部門からリーダーを務める社員が集まったわけですが、MRの2人は別として初めて会うメンバーばかりですね。

S.O.
そうですね。一番の若手は私でしょうか。わたらせ創薬センターの薬理研究所の研究員で、現在入社5年目です。昨年からテーマリーダーを任されています。薬理というのは、その名のとおり薬が効くかどうかを研究する分野で、創薬研究でも上流を担う部門です。

M.S.
S.O.さんたち研究部門が探索した新薬の候補を受け継いで臨床試験を実施するのが、私が所属する開発部ということになります。2014年に入社後、泌尿器、耳鼻科、呼吸器領域などの試験を担当し、6年目から国際共同治験における国内のプロジェクトリーダーを務めています。

T.N.
MRの業務についてはあえて説明することもないと思います。私とM.T.さんは世代も同じで担当エリアも近いこともあって、何度か話をしたことがありますよね。私は現在、東京都東部の3つの区をテリトリーするチームでリーダーを任されています。

M.T.
私のチームが担当するのは千葉県西部の3市からなるエリアです。入社6年目からチームリーダーを務めています。

T.N.
S.O.さんは入社4年目でリーダーを任されたようですけど、そんな若手のうちから任されることはよくあるのですか?

S.O.
もちろん、やる気があれば若手でも責任ある仕事を任せてもらえる風土はありますが、私は巡り合わせも良かったのだと思います。自分が担当していたプロジェクトから有力な化合物が見出され、そこから順調に新たなプロジェクトが動き出しました。現在は、数名からなる薬理チームのリーダーと、複数の研究所からメンバーが集まったプロジェクト全体のリーダーを兼任しています。

「個」の力だけに頼っていては限界がある。
担当エリアをチームみんなで
育てていこうという意識。

M.S.
杏林製薬では、チームワークのよさが一つの特徴になっています。しかし、そのスタイルは部門やチームによってさまざまです。MRの場合、個人とチームの活動のバランスはどのような感じですか?

T.N.
各営業所の方針によって若干違いはあると思いますが、私のところはチームの方の比重が大きいですね。

M.T.
私のチームも同じだと思います。チームリーダーになりたての頃は、ややもすると個人プレーに走りがちな感じがあったのですが、意識してチームミーティングの時間を増やすなど、メンバー同士が一緒に行動するように工夫しました。最近では、バランスのとれたとてもよいチームになったと感じています。

T.N.
私のチームは、自分も含めてMRは3人です。講演会の企画・実施などエリア全体に関わる活動などはどうしても1人だけでは対応できず、分担して進めています。担当するエリアを、メンバーみんなで育てていこうという感じですね。
研究や開発では、どのような形でプロジェクトを進めているのですか?

M.S.
臨床開発のプロジェクトは、私の所属する開発部と開発推進部、それに実務的な進行を担う外部のCRO(医薬品開発業務受託機関)が連携して臨床試験を進めていきます。開発推進部がシステムまわりなどの部分を担い、開発部が臨床試験全体を管理します。多い時期には二十人以上のメンバーが関わり、その全体を先導するのがプロジェクトリーダーの役割ということになります。

S.O.
わたらせ創薬センターでのプロジェクトは、薬理や合成、薬物動態、安全性など各研究所のチームが複合体のようになって動いています。私がリーダーを務める薬理のチームは若手ばかりの4人です。また、プロジェクト全体のリーダーも任されていますが、各チームの代表が常時連携してサポートしてくれるので、皆さんが想像しているほどプレッシャーはないと思っています。

チーム全体の方向性がぶれないように
時にはあえてリーダーシップを
意識することもある。

T.N.
リーダーにはいろいろなタイプがあると思いますけど、私は先頭に立って引っ張っていくというよりは、たえずチーム全体に目配りしてメンバーみんなで進めていこうというスタイルだと思います。

M.S.
私もT.N.さんと同じかな。臨床開発には幅広い知識と経験が必要となり、さまざまな専門家が連携して進めていかなければなりません。リーダーとしては、多様なメンバーたちの意見を集約するために、傾聴の姿勢を大切にしています。

M.T.
たぶんそうしたリーダー像は、杏林製薬という会社の雰囲気を考えてみても、部門を超えて共通するものではないでしょうか。ただ、チーム全体の方向性がぶれないように、時にはあえてリーダーシップを意識することもあります。

M.S.
いま私が携わっている臨床開発は国際的なプロジェクトのため、海外の部署や製薬企業との交渉も多いです。そんな場面では、先頭に立つリーダーとしての突破力も重要だと感じることがありますね。

S.O.
私も、最短ルートで目標に到達できるように方向性を定めていくことがリーダーとしての最大の役割だと思っています。そのために、他チームの先輩研究者と議論することもありますが、必ず理解してくれてサポートしてくれます。このあたりも杏林製薬らしさかもしれません
けれども、そもそも正直言って、私の中にはリーダーとメンバーという垣根はあまりありません。自分に足りない部分を、他のメンバーと補い合えることが杏林製薬のチームのよさ。時には他の部署の先輩にも相談して、チーム全体が納得する形で方向性を決めることを意識しています。

T.N.
それぞれが持てる力を発揮して、相乗的に前進していくような感じかな。たとえ若手でも得意とする特定の製品で素晴らしい実績をあげているMRがいるんですよね。そんなメンバーたちが代わり替わりリーダーシップをとりながら全体で成長していくのが、私が理想とするチームの形です。

優しいだけではない。
いつでも熱を秘めている。
それが、
杏林製薬のチームらしさかもしれない。

T.N.
いまリーダー像の話が出ましたが、杏林製薬“らしい”チームというと、どんなチームが思い浮かびますか?

M.S.
うーん、それは難しい質問ですね。一つ言葉をあげるとするなら、やはり「協調」でしょうか。互いにしっかり議論ができて、同じ方向に向かって進んでいける。そんなメンバーたちが多いような気がします。

S.O.
これは私が入社を決めた大きな理由でもあるのですが、この会社には温和で話やすい人が多いと感じます。それがチームの特色にも反映されているように思いますね。

M.T.
私も同感ですね。「チーム」というよりも「人」に対する印象なのですが、人柄がよくて温和な感じです。医療従事者の方や他社のMRからも、そこが「杏林さんらしい」とよく言われます。

T.N.
けれども、心に火がつくとみんな熱いのです。チームのミーティングでも、実績などリアルな活動の話になるとメンバーたちの表情が引き締まります。

S.O.
そこは研究者も同じです。ふだんは和気あいあいとしていても、話題がサイエンスのことになるとついつい白熱してしまいます。

M.S.
温和で優しいだけではない。底流には常に熱さを秘めている。それが杏林製薬のチームらしさかもしれませんね。