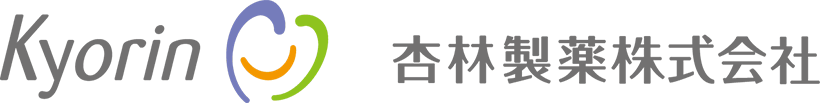特別編集ひとつとして、同じチームはない。
Profileプロフィール

J.W.
[MR]
東京支店
多摩第二営業所
チームリーダー
2019年 新卒入社
理学研究科

K.K.
[MR]
東京支店
多摩第二営業所
2023年 新卒入社
生物学科

Y.O.
[研究員]
わたらせ創薬センター
基盤研究所
2017年 新卒入社
理工学研究科

S.K.
[研究員]
わたらせ創薬センター
基盤研究所
チームリーダー
2013年 新卒入社
理工学研究科
杏林製薬には、一つとして同じチームはない。
リーダーとメンバーの関係も十人十色だと思う。

J.W.
先ほどお二人にわたらせ創薬センターの中を案内してもらって雰囲気はわかったのですが、実際にどんな研究をしているのかはほとんど想像できません(笑)。

S.K.
なるほど(笑)。私たちがいる基盤研究所は創薬の最上流、つまり、薬の一番最初の「種」を見つけることがメインの仕事となります。私がリーダーを務めるチームでは、呼吸器領域での新規テーマの創出をはじめ、現在3つのテーマの研究に携わっています。

Y.O.
チームのメンバーは私も含めて7人です。私はこれまで主に呼吸器疾患に関わる研究を担当しており、現在、S.K.さんも含め3人のメンバーで外部企業などとのコラボレーションによるプロジェクトを進めています。

J.W.
私たちがMRとして担当しているのは、東京の南多摩エリアです。私がチームのリーダーを務め、メンバーは3人です。そのうちの若手のホープがK.K.さん。まだ入社2年目ですが、すごい吸収力があってガムシャラで私自身も学ばされることがあります。

Y.O.
逆にK.Kさんにとって、J.Wさんはどんなリーダーなのですか?

K.K.
えっ、話しにくいな(笑)。見たとおりとてもスタイリッシュな人で、MRとしてすごく仕事ができる先輩です。私は、新人としてJ.W.さんが担当していた地区を引き継いだのですが、会う人誰もがJ.W.さんをほめてばかりで、ちょっとやりにくいんです(笑)。

S.K.
私から見ると、Y.O.さんは任せておけばあとはどんどん研究を進めてくれる頼もしいメンバー。いつでも明るく楽しく、チームの盛り上げ役でもあります。

Y.O.
S.K.さんこそパワフルな研究者ですよね。ときどき頑張り過ぎで心配になることがある。「もう少し私たちを頼ってもいいんだよ」と、この場を借りて伝えておきたいと思います(笑)。

そのような個人とチームの関係は、
MRの現場と共通する部分があるのかもしれない。

K.K.
同じ会社でも、研究職の人とはなかなか話す機会がないので、とても興味があります。普段はどのような形で仕事を進めているのですか?

S.K.
私たちが取り組む研究は創薬の中でも基礎的な領域となるので、基本的にはチームというよりも一人ひとりが進める研究の比重の方が高いと思います。

Y.O.
そうですね。現在、進めているプロジェクトでもメンバーそれぞれが調査や評価を行い、それを持ち寄って議論してチームとしての方向性を決めていくようなスタイルですよね。

S.K.
でも、どうだろう。私たちは2人とも大学の研究室に出向した経験がありますが、アカデミアの世界ほどは個人主義ではないと思います。私たちには新薬を創出するという大きな目標があるので。そこが製薬企業での研究の一番の魅力です。

K.K.
そういう個人とチームの関係には、私たちMRのチームと共通する部分があるかもしれませんね。

J.W.
確かに。メンバーには得手不得手があって、そもそも担当するエリアによって特性も違います。そのため、私は基本的にメンバーの活動は各人の裁量に任せるようにしています。一方、学術講演会の企画・実施など、エリア全体での杏林製薬のプレゼンスを高めるような取り組みについては、メンバー全員で力を合わせて進めています。

Y.O.
私たちも、大規模な実験などではお互いにサポートし合いますし、研究のことについては日頃から議論して情報を共有しています。そういう意味では、チームの力はとても大切だと思いますね。

S.K.
私は以前、感染症にかかって2週間ほど休んだのですが、その間、私の業務をメンバーみんながカバーしてくれて、プロジェクトは滞りなく進みました。とても嬉しく誇りに思ったのですけど、他部署の人から「あれっ、休んでいたんだっけ?」とか言われて、ちょっぴり淋しかったですね(笑)。

創薬研究は遠いゴールを目指す仕事。
チームとしてどうモチベーションを
高めているのか?

Y.O.
でも、営業では実績をあげるという目標もありますし、時にはリーダーシップを発揮しなければならない場面もあるのではないですか?

J.W.
私はチームリーダーを任されて1年半くらいなので、まだ手探りでやっているところがあります。リーダーとして意識しているのは、目標に向けてメンバーたちのベクトルを合わせることです。一人ひとりが当事者意識を持ち、モチベーションを維持することですね。昨年度「アプリコット賞」を獲得したので、2年連続を目標にしています。

Y.O.
それはすごい! 杏林の中でも優秀なチームに授与される賞ですよね。研究所でも目指しているのですが、なかなか獲得できません。

K.K.
創薬研究は目標にたどり着くまでとても長い歳月を要する仕事じゃないですか。どのようにしてモチベーションを高めているのか気になります。

Y.O.
うーん、研究のモチベーションですか……。

S.K.
Y.O.さんは常に創薬に対して高いモチベーションを持っている研究者だから、あまり意識したことがないのかもしれない(笑)。ただ、確かにゴールは遠いかもしれませんが、そこにたどり着くまでにはいくつものマイルストーンがあるわけです。目の前にある実験の成果そのものも一つの目標となる。リーダーとしては、みんなで一緒にディスカッションして悩みを聞いたりヒントを与え合ったりして、モチベーションを保てるように気を配っています。

J.W.
杏林製薬では、MRの詳細な実績を共有できるシステムがあります。私は、そのシステムを使って営業所のMR全員の実績を毎日チェックして、よい成績をあげた人には必ず声をかけて称えるようにしています。そうすることで自己肯定感が高まって、ポジティブな連鎖が広がっていけばいいなと思っています。

K.K.
じつは最近、私も影響を受けて同じことをするようになりました(笑)。

部門を超えて想いを交わせたのは貴重な経験。
杏林製薬ならではの新薬を
社会に届けていきたい。

S.K.
なるほど、そうしたエモーショナルな部分での気配りも、モチベーションアップには大切なんですよね。こうして異なる部門のメンバーと話し合ってみると気づかされることがたくさんあります。

J.W.
こちらこそ自分たちが日頃扱っている新薬を創っている研究所の人たちと率直に話ができるのは貴重な経験です。同じ杏林製薬のチームとして共通する部分がたくさんあることがわかって嬉しいですね。

K.K.
杏林製薬には優れた新薬がたくさんありますが、やはり自社開発したオリジナルの新薬には私たちMRも特別な思い入れがあります。医師から「あの薬が効いて、患者さんが喜んでいたよ」といった声を聞くと、すごく嬉しくて誇りに思います。

S.K.
そんな話を聞くと、私たち研究者のモチベーションも高まります(笑)。杏林製薬ならではの新薬を、ぜひ自分たちの力で創り出したいですね。

Y.O.
その夢を叶えたくて杏林製薬の研究者になりました。患者さんに新薬を届けるために、これからもみんなの気持ちを一つにしてチャレンジしていきたいですね。